天空の宮脇先生に見つめられて1年
7月16日は宮脇先生が天空へ旅立って1年目。年のせいなのか、時の流れが若い頃と比べると倍以上速く感じられるこの頃の私です。
先生の命日を前にして、この一年を振り返ってみました。森びとスタッフとして、そして一人の人間としてどうだったのか?。先生は常々、「本物になれ!、死ぬ気になってやれ!」と檄を飛ばしてくれました。「本物とは、幾多の困難を乗り越え、長く生き続けること」と教えられていました。

こんなエピソードがありました。植樹祭の前日、サンレイク・草木の一室に宮脇先生、高橋さんと私が寝ることになりました。先生は、中国地方から山梨県を経て宿に遅くなって到着しました。時間を惜しむように布団に入って、ペンを走らせていました。私は緊張していて他の部屋で、仲間と酒を飲んで過ごしました。翌朝目を覚ますと先生は、もうテーブルに向かいまたペンを走らせていました。(高橋さんも)そんな二人を見てとても気恥ずかしさを覚えたのでした。本物になることとは、日常のあらゆる場面で、自分自身との闘いがなければ実現でき得ないのだと感じたのでした。
そんな私が、6月の熱波で保管中の苗木を枯らしてしまいました。異常な高温が続いたにも関わらず、水やりに真剣に向き合わなかったからです。茶色くなった苗木を見て、愕然としました。人間の都合を優先していると木は育てられません。と、頭では分かっていたのですが。
宮脇先生の教えの中で「人間は植物に寄生して生きている」と言われていました。いま森びとでは「森に生かされている」と表現していますが、植物が無かったら、どんなにお金を持っていても、権力を持っていても生きていけません。植物だけが生産者で、人間をはじめ全ての動物は植物に寄生した消費者だと、先生は単純明確に説いています。人間一人が生きていくために27本の成木が創り出す酸素が必要だと言われています。こんなことを多くの人に理解してもらえれば、気候危機の社会に大きな光が差し込むでしょう!
足尾は今、お盆を迎えています。森びとスタッフが手向けた花が、旧松木村の先祖の墓石に供えられ、それに見守られながら「民集の杜」が広がっています。その入り口に宮脇さん、岸井さんの祈念樹のイヌブナ、ホウノキが植えられています。いつまでも天空から森びとを見守っていてください。
森びと栃木県ファンクラブ・橋倉喜一































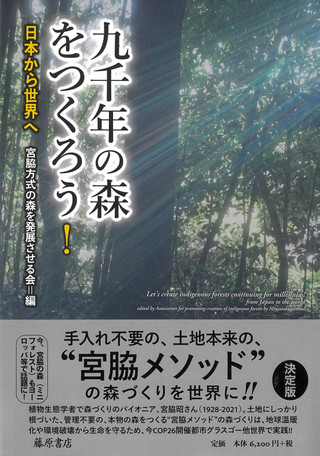
















最近のコメント