地球人の暮らし方は森の中に潜んでいる?
5月19日に開催する第37回「足尾・ふるさとの森づくり」では“ゴミを極力無くす”考えのもと、昼食は今までのように弁当ではなく、おにぎりとおかず、汁物、デザートの提供をしていきたい。僅かなことかもしれませんが、このままの暮らしを継続いていくと巨大化する異常気象によって人類の生存が脅かされるかもしれないことを考えていただくそのきっかけにしたいと願っている。昼食後のトーク&トークでは、地球温暖化にブレーキをかける森づくりと暮らしについて宮脇昭先生と話し合っていきたい。参加者のご意見に期待したい。
 ところでトランプ大統領は「パリ協定」から離脱したままたが、アメリカ・ワシントン州シアトルのレストランでは、今年7月1日からプラスチック製のストローやフォーク、スプーン等を消費者に提供しないらしい。また、MLBやNFLでのスタジアムでもそれらは廃止になり、スターバックスでも徐々にそのように移行していくらしい。
ところでトランプ大統領は「パリ協定」から離脱したままたが、アメリカ・ワシントン州シアトルのレストランでは、今年7月1日からプラスチック製のストローやフォーク、スプーン等を消費者に提供しないらしい。また、MLBやNFLでのスタジアムでもそれらは廃止になり、スターバックスでも徐々にそのように移行していくらしい。
 アメリカでは毎日5億本のストローが消費され、そのほとんどが処分され、その一部の行き着く先は鳥やウミガメの胃の中という。スコットランドでは2019年までにプラスチックのストローを無くす計画であり、台湾でも2030年までに使い捨てのプラスチック製品を禁止する予定だ。日本でも一部の方々は暮らしに「エコ」を取り入れているが、行政としての取り組みになっていない。
アメリカでは毎日5億本のストローが消費され、そのほとんどが処分され、その一部の行き着く先は鳥やウミガメの胃の中という。スコットランドでは2019年までにプラスチックのストローを無くす計画であり、台湾でも2030年までに使い捨てのプラスチック製品を禁止する予定だ。日本でも一部の方々は暮らしに「エコ」を取り入れているが、行政としての取り組みになっていない。
先日、東京大学名誉教授・山本良一氏は「人類に残された時間はあと20年程度。対策を引き延していけば本当に手遅れになる」と地球温暖化への対策を訴え、さらに「北極点の海氷が年々減り続け、温暖化による影響がさらなる温暖化を招く『ポジティブ・フィードバック』は始まる。2012年のスーパーハリケーン『サンディ』、2013年のスーパー台風『ハイエン』は温暖化の影響によるもの。去年の九州北部豪雨では1日に1.000ミリという雨が降った。こうした豪雨がもし関東に襲来したならば、荒川が決壊して都心が水没、壊滅状況になる。そうした事態が起きても不思議ではない」(筆者まとめ)と警告している。
 「今だけ、金だけ、自分だけ」という風潮が蔓延る切ない社会、そして浪費が暮らしに蔓延している大量生産大量消費の生活スタイル。けれども多くの方々は、さらに浪費社会を追い求める政治と経済を推進する安倍政権に期待をかけている気がする。私たちは15年前から山本名誉教授のような警告に耳を傾け、地球温暖化にブレーキをかけていくことに向き合っている。樹木の力を借りて少しでも二酸化炭素を削減してほしいと願い木を植えている。しかし、市民の植林活動や良識的な企業の二酸化炭素排出削減策では地球温暖化にブレーキはかけられても世紀末には生存が不安定だ。このまま温暖化が進むととんでもないしっぺ返しがやってくる気がする。政治による大胆な温暖化防止策が求められている。
「今だけ、金だけ、自分だけ」という風潮が蔓延る切ない社会、そして浪費が暮らしに蔓延している大量生産大量消費の生活スタイル。けれども多くの方々は、さらに浪費社会を追い求める政治と経済を推進する安倍政権に期待をかけている気がする。私たちは15年前から山本名誉教授のような警告に耳を傾け、地球温暖化にブレーキをかけていくことに向き合っている。樹木の力を借りて少しでも二酸化炭素を削減してほしいと願い木を植えている。しかし、市民の植林活動や良識的な企業の二酸化炭素排出削減策では地球温暖化にブレーキはかけられても世紀末には生存が不安定だ。このまま温暖化が進むととんでもないしっぺ返しがやってくる気がする。政治による大胆な温暖化防止策が求められている。
 来月19日の植樹祭をスタートにして、今年は“原発に頼らない 森と暮らす街づくり”へジャンプしたい。体験したことのないライフスタイルとその社会を描くことになるが、そのヒントは命の源である森が与えてくれる。その防止策は世界の森びとの連帯によって実現できる。(事務局 小林 敬)
来月19日の植樹祭をスタートにして、今年は“原発に頼らない 森と暮らす街づくり”へジャンプしたい。体験したことのないライフスタイルとその社会を描くことになるが、そのヒントは命の源である森が与えてくれる。その防止策は世界の森びとの連帯によって実現できる。(事務局 小林 敬)





























































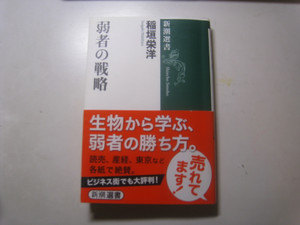

最近のコメント